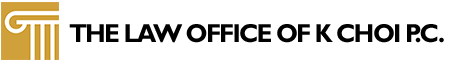一般的に「児童身分保護法(CSPA)」は、ある子どもが21歳未満で「同伴子女」として申請に含まれていたものの、長い審査期間のうちに21歳を超えてしまった場合でも、子どもとしての資格を維持できるようにする法律として知られています。たとえば、就労ベースの永住権申請や米国市民による家族ベースの申請(市民権者による子ども申請など)では、主申請者の同伴子女は常に未婚かつ21歳未満であることが必要で、21歳を過ぎると資格を失うおそれがあります。
では、21歳未満で永住権保持者(LPR)の未成年子として申請されていた子どもが、21歳を超えた後に親が市民権を取得した場合はどうなるのでしょうか。単に「市民権保持者の成人の子(F1)」にカテゴリーが切り替わるだけなのか、それともCSPAの適用により「市民権保持者の未成年子」、つまり「近親者(Immediate Relative)」の扱いを受けられるのでしょうか。近親者になれるかどうかは、優先日を待つ必要の有無や、不法滞在中であってもグリーンカードを申請できるかどうかにも影響するため、実はとても重要な問題です。
この点について、移民法には直接的な定めがありません。F2B(永住権保持者の21歳以上の未婚子)のカテゴリーでは、親が市民権を取得してもF2Bのままでいる選択ができる、いわゆる「オプトアウト」規定が設けられていますが、F2A(永住権保持者の21歳未満の未婚子)が親の市民権取得後に近親者カテゴリーへ移行できるかどうかについては明示されていません。
これまでUSCISは、F2Aの子が21歳を超えた段階で親が市民権を取得した場合は「F1(市民権保持者の成人の子)」にカテゴリーが変更されるとしてきました。BIA(移民控訴局)とUSCISは、CSPAに関するこれまでの解釈から、この方針が正しいと見なしてきたのです。
ところが、最近連邦控訴裁判所(第9巡回区裁判所)で、USCISとは異なる判決が下されました(Tovar v. Sessions, No.14-73376 (9th Cir. 2018年2月14日付))。この判決によれば、このようなケースでもCSPAが適用され、子どもの年齢を「未成年」として扱うことで、近親者(Immediate Relative)扱いにしなければならないというのです。つまり、市民権保持者の「未成年子」としてみなされることになります。
連邦裁判所は、子どもの年齢は実年齢だけでなく、CSPAによる「法的な年齢」を考慮できると判断しました。また、F2Bにはオプトアウト規定があるにもかかわらずF2Aにはないのは、F2Aの場合、親が市民権を取得すれば近親者カテゴリーに移行するという想定があるからだと説明しています。
いずれにしても、子どもが年齢超過によってF1カテゴリーに切り替わると長期間待たなければならない可能性がありますし、もし子どもが不法滞在状態であればさらに複雑な状況に陥る可能性があります。したがって、このような事態を回避する方法があるというのは、大変喜ばしいことです。
このケースでは、F2Aの子どものCSPA上の年齢を所定の計算方法で求め、その年齢が21歳未満であれば、そのまま近親者カテゴリーに該当します。すなわち、CSPAの計算上21歳未満であれば、市民権保持者の「未成年子」として扱われるわけです。
ただし、この判決は連邦高等裁判所(控訴裁判所)のものであり、全米に一律適用されるわけではないという点は残念なところです。